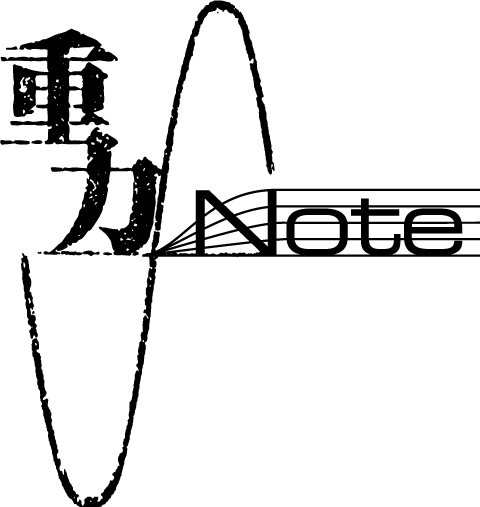▷Project
2013年に迎える寺山修司没後30年に向けて、重力/Noteでは「寺山を知らない世代(83年以降生まれ)」を中心に、寺山の残した様々なテキストを演劇化する試みを重ねてきた。寺山の仕事には世間一般に知られているカルチャーとしての《テラヤマ・ワールド》がある一方、高度成長を迎えていた当時の日本社会がもたらした生活様式の激変の中において、それぞれの人々に生じていた亀裂―例えば故郷・都市・家族といったものとの葛藤に寺山は眼を向けていた。この上演では寺山のテキストに加えて、晩年の寺山を追った評伝『職業◉寺山修司』(著者:北川登園)を組み合わせることで、ドキュメンタリーとフィクションが交錯する演劇性を追究。寺山修司の言葉に、新しい響きを取り出すことに挑戦した演劇作品。
▷あらすじ











会場 STスポット横浜
原作 寺山 修司(『ある男、ある夏』ほか)
北川 登園(『職業◉寺山修司』)
出演 石田 晶子 稲垣 干城 井上 美香 瀧腰 教寛 立本 雄一郎 邸木 夕佳 山田 宗一郎
構成・演出 鹿島 将介
照明 井坂 浩
音響 安藤 達朗
舞台美術 青木 祐輔
衣裳 富永 美夏
運営 福田 英城 増永 紋美 重力/Note制作部
協力 長谷川事務所 アマヤドリ
主催 重力/Note



どうも、《寺山修司》を知らないということ
「寺山修司を知らない」と、うそぶいてみたい。
事実、そうなのだった。1983年生まれの私が、生前の寺山を知るはずがない。だが、どうしたことか気がつかないうちに——それもなんとなく気の赴 くままに身につけた、例えば読書という趣味が、映画鑑賞という趣味が、音楽という趣味が——いつの間にか《寺山修司》という人物に到達しているのだ。あた かも私たちの身の回りにある、あらゆるものの源流を押さえられてしまっているかのように、気がつくとテラヤマは、いる。
舞台藝術に携わっていると「面白いけど、それはもうテラヤマがやっているよね」という言葉が、しばしば立ちはだかる。大概、その言葉を口にした者自 身も具体的な根拠をあげられるわけではなかったりするのだが、それでも妙な説得力をもって口端にのぼっては、いまなお前線で捻りだされた渾身のアイデアを 一蹴する。ウソカマコトカ知らないが——どうやらテラヤマが一通りやり尽くした、らしい。いつどこでテラヤマに影響/浸食されたのか、自覚がないだけ ギョッとする。全く、これには困っている。
それでも「寺山修司を知らない」と、あえて言おう。
かつて彼が東北の地から眼差した東京という都市、決別するかのように後にした故郷、血をめぐる葛藤、どこでもない世界への憧れなど、いま彼のテキス トに触れるたびに想起されるこれらの反復された衝動を前に感じるのは、共感という名の身近さよりも、少し距離のある何かだ。彼の死んだ年、浦安の埋立地に は東京ディズニーランドが誕生しているが、ジンタのメロディがエレクトリカル・パレードのそれへと移り変わり、さらに磐石だと思われていた夢の国が液状化 でひび割れた時代を、私たちは生きている。
とりあえず、舞台上にちゃぶ台を一つ置くところから始めたいとだけ思っている。寺山の愛憎がむけられたこの家具ですら、もはや私たちにはフィクションなしでは見つめられない何かなのだ。
鹿島 将介
▷關智子さんによる劇評
谷(竜一)氏は本公演の会場であるSTスポットへ向う途中をレポートし、そこで彼が想像していた「テラヤマ的なるもの」が裏切られたことに「愕然」としている。その後、「テラヤマ的」なものへの期待は容赦なく打ち砕かれ、結果として公演自体はテラヤマとの「距離」を感じさせる、決して「スリリングとは言いがたい」ものであり、「「テラヤマをやっている」と言うにはあまりに丁寧」としている。筆者はこの意見に概ね賛成である。しかし、そこから導き出される作品に対する考察の結論はほとんど逆である。谷氏は「この有名多彩でありながら、かつ謎めいた寺山修司像に新たな光を当てようという試み」としているが、筆者はむしろその試みを超えた先の問いを投げかけていたのではないかと思う。すなわち、「寺山修司像に新たな光を当てる試みは可能なのか?」というものである。この問いは、作品自体と観客の両方に投げかけられている。
本公演は寺山修司とその周辺にあるテクストを用いて構成された、いわゆるポストドラマ的な演劇作品である。そのテクストはほとんどが随筆、新聞記事、小説や評論などの戯曲とは異なるものであり、それらの言葉を発しながら俳優たちはそれと関係あるようなないような行為や表情をし、谷氏の言葉を借りれば「遊戯」している。
その「遊戯」は手を変え品を変えルールを変え、延々続けられる。例えば、盥にいったままうさぎ跳びをする男と彼に似非英語で話しかける女。例えば、三人の女が棺あるいは神輿のように担ぐちゃぶ台。例えば、ちゃぶ台の周りで林檎を分け合う男女とその脇に立ち大声で物語る男、などなど。挙げ出すとキリがない。
この「遊戯」に論理的な展開はない。最後は寺山修司の葬儀で読まれた谷川俊太郎の弔辞で終わるのだが、それも物語のクライマックスとなるような盛り上がり方は見られない。これまでの「遊戯」の延長であるかのように淡々と俳優たちに回し読みされ、彼らは一人ずつ(物理的な)劇場の外へ出て行き、終わる。「スリリング」とは程遠い公演であるのは確かであり、その間テラヤマ的、あるいはアングラ的な雰囲気はほとんど見られないのも事実である。
このような公演になった理由は、演出の鹿島将介氏の言葉から読み取れる。「寺山修司を知らないと、うそぶいていみたい」。
筆者もそうだが、鹿島氏を筆頭に本公演の関係者の多くは寺山修司の没後あるいはその少し前に生まれ、厳密にはテラヤマ的なるものを知らない、と言える。だが、演劇をやる上でそれは許されない。現代日本演劇の根幹に染み込んでいるテラヤマ的なるもの、それを体験せずに、あるいは知識としてもテラヤマ的なるものを知らずに演劇に関わることは、まだ時期的に不可能だと言える。恐らく、本当に全く寺山修司を知らずに寺山修司を扱った作品を作れるのは、もっと後の世代だろう。
今、本公演の制作者たちがテラヤマ的に寺山修司の作品を扱っても、内部からも外部からも「これはテラヤマではない」という意見が出てくるのは必須である。近づけようとすればするほど、遠ざかる。かと言って、完全に違うものとして、全く新しい目線で寺山修司を扱おうとすれば、それは嘘になる。すでにテラヤマ的なるものが個々人の中でイメージとして出来てしまっており、知らないが知っているという微妙な距離感が寺山修司との完全な断絶を不可能にしている。
この距離感は、空間演出と衣装に見て取ることができた。本公演はSTスポットを通常とは逆使い、すなわち、通常は舞台となっている側に客席を設け、調光室、音響室、二箇所の出入り口が客席から見えるようになっていた。STスポットは小さな劇場である。俳優が七人もいれば舞台は埋まってしまい、窮屈な感じがする。俳優たちのツナギのような衣装と調光室から時折見える人影(実際には照明係や音響係の人なのだが)のせいか、刑務所や収容所、あるいは人体実験の現場を連想させた。
だが、その窮屈な拘束された印象は舞台空間全てを支配していない。それは、劇場に浮かぶ雲や青空のような衣装の色彩の働きによって、解放感も同時に演出されているからである。閉塞感と解放感。これは、鹿島氏の言葉からも読み取れる、寺山修司という存在に対するある種の印象ではないだろうか。寺山修司という大きな存在が既に没しているという中で演劇を行うことは、ある種の解放である。だが同時に、没してしまっているが故の膨張したイメージとまだ歴史にはならないという微妙な距離が、彼を扱う上で閉塞感を感じさせるものともなる。
俳優の一人が、北川登園の「寺山修司が逝って、もう、二十年になる」という言葉を発した時、その「もう」に含まれるのはこういったアンビバレントな感覚であり、その感覚が演出にも表されていた。
では、そのような両義的な場所で、俳優たちは何者として「遊戯」していたのか。寺山修司や北川登園の言葉を発話するが、彼らになるわけではない。俳優はあくまで彼らとしてそこにおり、発話はあくまで「遊戯」の一部である。時折、(盥で天井から流れ落ちる水を受け止めながら)号泣したり、(寺山の小説の一部を朗読しながら)激怒したりもするのだが、その感情にいたるまでのプロセスがあるわけでもなく、次現れた時にはケロリとしているため、それも全て遊んでいたのだと分かる。彼らは「遊戯」するためだけにそこにいたのだろうか。
筆者には、何者かの到来を待っていたように思われる。サミュエル・ベケット(Beckett, Samuel)の『ゴドーを待ちながら』(Waiting for Godot)の登場人物、ヴラジミールとエストラゴンのように、彼らは何者かの到来を待ちながらその暇を潰すために「遊戯」しているのである。こうしていれば、現れるのではないかと思いながら。そして言うまでもなく、その何者かとはテラヤマである。そして俳優だけではなく、観客もまた彼を待っていたのではないだろうか。本稿の前半で述べたように、谷氏は「テラヤマ的」なものを期待して劇場を訪れた。寺山修司を扱った作品を上演するという時点で、彼を知る観客の多くは一瞬でもそれを期待するだろう。ひょっとしたら、「テラヤマ」が体験できるのではないか、と。しかし、ゴドーは現れないものである。
いくつかの試みは見られた。突如劇場内が暗転し、「見えない演劇」という言葉が発せられる、ちゃぶ台の前に無表情で座り、寺山修司の言葉が語られる、など。その時俳優は、テラヤマが現れるよう呪術的な儀式を行うイタコであり、観客はテラヤマが降臨するのを待つ者である。こうしていれば、ゴドー=テラヤマが現れるのではないだろうか。前のルールではダメだったが、この「遊戯」のルールなら大丈夫なのではないか、という期待は高まる一方である。
ヴラジミールとエストラゴンは、「行こう」「あぁ、行こう」と言いながらその場を動かず、ゴドーを待ち続ける。本公演の最後では、俳優たちは「×月×日、いつもと同じ」と言いながら劇場を出て行く。作品が始まる前にいた場所へと戻っていくのだろう。そしてまた劇場へ戻って来て、テラヤマを待つのだ。「いつもと同じ」ように。閉塞感と解放感、絶望と希望が同時に生まれるこの場所で。
關智子『ゴドーとしてのテラヤマ』2012.11.01.より抜粋
【寺山修司 Shūji Terayama 1935~1983】
1935年生まれ。青森県出身。 詩人、歌人、小説家、劇作家、演出家、映画監督、シナリオライター、文芸評論家、エッセイスト、写真家、ボクシング評論家、ジャズ評論家、競馬評論家など 多くの肩書きを持つ。総じて「僕の職業は寺山修司です」と自称していたと言われている。67年より演劇実験室「天井桟敷」の主宰として演劇活動を展開。市 街劇をはじめ様々な実験的試みはなかば伝説化されている。またドイツの国際実験演劇祭やフランスのナンシー演劇祭など、日本の劇団が海外に進出していくこ との先鞭としての役割を果たした。代表作に評論『書を捨てよ、町へ出よう』(67)、映画『田園に死す』(74) 、戯曲『奴婢訓』(78) などがある。83年没。
Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.