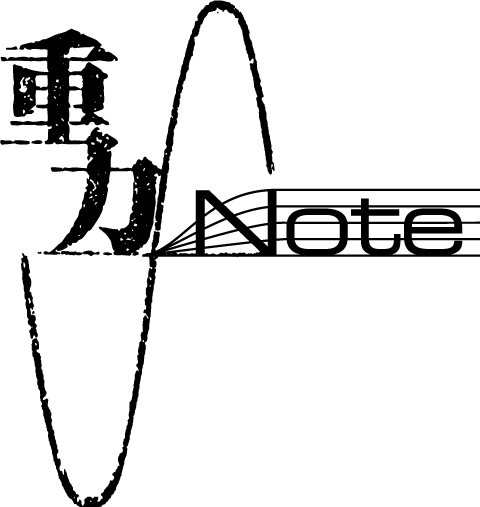▷「敗北の演劇」小史(2009年8月『演劇人 25号』掲載)
東京ディズニーランドが埋立地に姿を現した年、それはまた寺山修司が死んだ年でもあったが、その年が私の生の始まりであることについて想いをめぐらせる時がある。そこには、私の生が引き受けざるをえない時代的制約の始点が間違いなく存在している。この偶然は、何も私一人だけに与えられたものではないことはわかっているのだが、何やら否定し難い確かな引力をもっている。
この引力は何か。各々の象徴的な事柄に説明を求める以前に、この見えざる力に対して私自身の根深い必要が共犯的に動いているのを感じる。つまり私自身が進んで身を委ねているふしがあるということだ。根拠への志向。その無意識的な欲望の根を覗き込もうとすると、たちまち深い喪失感が漂っていることにおもわずたじろいでしまう。私の生の根拠には常に喪失感と、その取り返しようのない隔絶が基礎条件となっている気がしてならない。もし何か語ることができるとしたら、ここから始めるしかないように思える。
『物質試行49 鈴木了二作品集』を眺めていると、その一つ一つの建築物がまるで廃墟のように撮影されていることに気づく。そこには、がらんどうに吹く風の心地と、不思議な懐かしさがあった。かつて十九世紀パリの街並みをいち早く廃墟の如くとらえ、その被写体である建築物の表面に微かに残影する生の痕跡を写真におさめたアッジェの姿が浮かぶ。しかし何かが違う。順路が違うのだ。アッジェの写真は崩壊と忘却にさらされている街並みに対する哀悼的試みであったが、鈴木了二のそれは、始まりの時点から終末の姿を備えている。いや、むしろ終わりから思考された建築といってもよいのかもしれない。この廃墟的感覚は何なのだろうか。
廃墟に対する望郷、それが私の奥底にある。半世紀以上前にアーレントが「廃墟」と呼んだものは崩壊した十九世紀的伝統や文化だけを指したのではなく、現在を生きる私たちの精神的な原風景にまでおよんでいる。「世界の喪失感」とアスファルト。予言的に語られていたように、今では喪失それ自体が遥か以前に忘却されており、「忘却の忘却」と呼ばれるまで加速されたものとなっている。そのことによって何か根源的な始まりを奪われているという感覚は、日常生活の中ではごく小さなゆらぎに等しい。だが、その小さなものに眼を向けるには何か虫メガネのような仕掛けが必要である。その役目を作品が負うならば、廃墟性が作品に潜むことの意味とは何か。
鈴木にとって建築は一回性の「出来事そのもの」であり、それは「視覚」の中に「触覚」を含みこむことで、連続的な時間概念に亀裂をもたらすことを目指している。この過程を「人類史的記憶」から「物質的記憶」への置き換えとし、この転換への働きかけが「忘却」にさらされている「記憶」の救出の契機となる、としている。この試みが成功しているとするならば、その相貌が廃墟的であることは極めて象徴的な結合と言えるだろう。ここにおいて廃墟的な作品を作り出すことは、如何にして実在性をもった現実を取り出してみせるかという社会的な役割だけでなく、体感する能力の覚醒を促すとともに、「記憶」の救出を経た先にある精神的なものの救出が目指されており、重層的な目的を兼ね備えたミメーシスとなっている。つまり知覚そのものの救出が、私たちの喪失感からの回帰へと繋がっているのだ。そのための仕掛けとしての廃墟的フィクション、ここに一つの深い必要を感じる。
この「廃墟」との遭遇は、演劇の世界ではどのような形で表れているのだろうか。
端的にいって、それは〈役〉というものに対する概念に大きく影を落としているように思う。確かにスタニスラフスキー的な取り組み、すなわち〈役の感情を生きる〉ということを支えに演じられることへの批判的実践は多く為されてきたし、その対になるものとして〈身体〉が取り上げられてきた。それによって演劇が「誇張された文学」から脱することにも成功した。その文脈においての〈役〉は、ずいぶん前に絶対性を失っているだろう。だが、もっと何か根本からその成立過程に不信感が漂ってはいないか。役の廃墟化。否、さらに遡った域での不信があるのではないか。
「ぼくは初めて語るということがーー初めてといってもいいくらいですーー、世界を提示することの根本にあるんだということが了解できたように思うのです。しかし、人々に語られることによって世界が世界でありうるというとき、それはかつて、その語りあいによって「人間的」世界になりうると言われたんですね。それがここでは、もっとも「非人間的な」経験と記憶のありかから「語り」が引きずり出されている。そうだとすれば、そこに立ち現れている「世界」というものの姿ですね、ぼくらが受けとらなくてはならないのは。」
(【対座】吉増剛造・市村弘正『この時代の縁で』)
アウシュヴィッツの生き残りを取材した映画『SHOAH』についての市村弘正の関心は、証言者たちの「語り」について向けられている。市村は「生きる態勢のいちばん根幹にかかわるところ」において、また「人間が人間であること、そのぎりぎりの条件」において「語り」が問題になると発言している。語りの中に立ち現れる存在の証明、そこで証明されているのは語られる世界と語り手の主体である。演劇の構造に置き換えるならば、〈物語の世界〉と〈役〉に関係する者だ。これらの関係は、先の発言でいうところの「語りあいによって「人間的」世界になりうる」ことを信じることができた人々によって成立していた。演劇の実践における、能をはじめとした伝統芸能などからの「語り」の引用が効力を持っていた頃の人々の精神には、まだこの語りと世界との関係への信頼があった。それは「世界の喪失」を目の当たりにした者たちの「人間が人間であること、そのぎりぎりの条件」を死守するための闘いでもあったろう。だが現在私たちが遭遇しているものとは、市村が見つめている方の世界の経験である。すなわち「もっとも非人間的な経験と記憶」が基礎条件となり、それを語るには「引きずり出され」るような心地を強いられる世界の経験。そこでは〈物語の世界〉にも〈役〉にも関係を取れないものが立ちつくしている。関与することができずに宙吊りにされた俳優。この、〈物語の世界〉と〈役〉との境界をむすぶ口(俳優)は、もはやベケットの『わたしじゃない』のような在り方でしか存在できないのである。あのまくしたてるような速さで己の存在を否定し続ける口を「二十世紀の口」と市村は評している。
現代劇の俳優は「一体この俺が何を演じられるというのか」という問いを己に投げかけない限り、舞台に立つことはできないはずだ。そして、その究極的な答えとは「何も演じることはできない」である。実在性を備えた人間像を顕現させることが俳優の役目であるならば、かろうじてそこに現れるのは「二十世紀の口」か、私たちのよく知るあの廃墟の住人たちであろう。彼らは言葉の根に近づけない絶望に苛まれている。どこまで揃っても辞書的語源の岩盤を突き破れない不安感と、言葉の根が生活感覚からも収奪されてしまっている喪失感。それらのヒステリックな反動としての狂騒や無意味への誘惑。超絶技巧の名優を目指す者もいない。かつて言葉の根と強固な結びつきができた時代の俳優たちとは似て非なるものとなるだろう。むろん、これらの実感を意図的に無視すれば話は別であるが。
私は彼らの演技がどのようなものかをイメージしたい。きっとそれは劇的において挫け、存在において敗れる演技ではないだろうか。その演技の成否は、如何に舞台上で劇的(芸)と存在の二極間を〈運動〉してみせるかにかかっている。まず彼らは朗々と役を演じてみせようとするだろう。しかし、私たち観客の知覚がそれを許さない(観客もまた廃墟の住人である)。彼はたちまち役を諦め存在へと逃げこむが、ここでもすぐに追い払われてしまう。「忘却の忘却」には存在の重みを実感するだけの時間的余裕がないのである。その姿は必死であればあるほど滑稽だ。これら二極の敗け方において観客は俳優を認めるだろう。つまり現代劇の俳優の演技とは、自明性としての物語世界や歴史的根拠の前に絶えず敗北し続ける身振りのことである。これは廃墟における我々の似姿なのだ。俳優たちがこの運命を引き受け、翻弄してみせる姿に、私たちは確かな現実と、その向こうにあるユートピアを見るに違いない。この敗北の形式の中に、現在の私たちの実在性があるのではないだろうか。

▷《関係》の詩学―地点はいかにしてアルトーを拷問したか
(地点『−−ところで、アルトーさん』舞台評・2011年2月『とまる。』掲載分を一部加筆修正)
世界演劇史上の遺産に敬意を払う一方で、統一された物語や登場人物の心理から逃れてゆく劇構造を展開する劇団「地点」――その活動を記述しきることは、本質的な意味において不可能だろう。新たな歴史の構築と解体、その現象を同時におこなう両義的な存在として投げ出されている前衛、それが劇団「地点」である。多くの観客が失語状態に陥っている彼らの作品に対して、はたして何を語ることができるのか。そこから始めるには、劇構造とそれを支える俳優の仕事について触れる必要がある。
演出の三浦基氏は、テクストを行使することによって時空間に関与していくことを俳優の仕事だとしているが、その著書『おもしろければOKか?』の目次をみると、「台詞/発語/俳優」と「役/言葉/身体」の二つのベクトルから「演劇」へと到達する構成になっている。 この手続きによって見出されたものは、文中にある「《関係》が存在した」という一語に収斂されているとみてよい。ここには大きくわけて二つの演技論上の変遷があったことがわかる。一つは俳優の演技それ自体を解体・細分化すること(内面の分裂状態における実存の探究)であり、もう一つは俳優の身体や舞台空間で生まれる現象を使って外側に多層的な《関係》を形成すること(瞬発的な《関係》の詩への探究)である。これらは、それぞれ別方向の志向性を持ちながらも、総じて最小単位の「演劇」の要素を導きだすプロセスであった。ここ数回の公演において、戯曲ではなくエッセイや演劇論といったテクストを使っているのは、「物語の登場人物同士によるドラマツルギーの展開に一切頼らないで、舞台空間において繰広げられる言葉や身振りを通じて刹那的に生じる《関係》の連続によって演劇は成立しうるのか?」という問いの実践だといえる。
かくして観客は、アルトーのテクストが《関係》される瞬間に立ち会う。水面に反射した光が、声を運ぶ電波のように浮かびあがる。俳優がそこかしこにマイクを向けることによって、観客はそこに生じている音へと耳を傾けることになるだろう。また目に見えないノイズや波長といったものへのアプローチが、俳優の声においても志向されていた。本来は一切見えないはずのものが、舞台空間上のあらゆる手法を駆使してテクストに《関係》されることによって、かろうじて生まれた一瞬間としていまそこにあるということへの厳かさ。アメリカを彷彿とさせるポップアート調に拡大された肖像画や原色ギタギタの照明、歌謡曲などによってジャンクさに彩られたこと、これらをアルトーの言葉への解釈として留めてしまうのは貧しいだろう。むしろアルトーの言葉が、それらの表現をも許容していることに目をむけるべきである。それらはテクストに対する新解釈と呼ばれる類いのものではなく、アルトーの言葉を破局させた先にあるものだ。形式と体感されたもののあいだを問うこと、ここにこそ、いまだ名づけえぬものへの思考がある。
そうした一方で、驚くほど素朴な演技の採用が、例えば手紙による手旗運動をどうみるか。一般的にみれば下手と評せられても憚らない身振りが、構成の妙味によってつかの間の気楽さとともに受け取ることができてしまう。三浦氏の演出において際立っているのは、テクストの解釈や舞台空間の抽出力以上に、まず俳優による演技の上手・下手や強弱をもろともしないシーン構成の絶妙な配置とその圧縮力だと言える。ここにおいて注目するべき点は、俳優たちを一つの形式の中で競争させないように構成されていることだろう。ここには先行世代の前衛たちにあるような、統一された様式への信仰や絶対性はない。逆に諸形式の氾濫とそれらを消費的につぎこんでいくことを厭わない態度があり、これら全てが過ぎ去ったあとにくる虚無的な停滞をも劇構造の内に含んでいる。
ただし、今回の公演ではシンプルかつ素朴すぎる演技を幾つか許容したことによって、複雑多岐にわたって展開された《関係》の価値の数々が、等価的にフラットかつ消耗的なものへと反転してしまい、上演のプロセス全体をしょうもないものとして印象づけられかねない危うさを孕んでしまっていた。その構造的な問題として、アルトーの肖像画とプールによって舞台空間の中心を決定づけすぎたことが、一つの原因になっている。その結果、俳優間で《関係》を形成する場所に自由度がなくなり、単体で剥き出された状態で演技する時間が増え、結果として個人の技芸による負担が増してしまった。ワンマンショー的な形式は、アルトーの冗長で濁流的な言葉のエネルギーに相応しいものである一方、俳優が技術上でも絶対的な存在であることを次第に要請させられる知覚構造を抱え込んでしまう。俳優の個性が彩り豊かに発揮される一方、舞台空間の現象を縦横無尽に素材化して《関係》を抽出していた演劇的自由度は限定され、その結果として、観客が知覚できるイメージは俳優の演技を基点にする層に留まることになった。また本来の持ち味でもある、演技上の共存性が損なわれていくというジレンマに陥っていた。それでも後半に決定打を欠いていた京都版と比べると、東京版では終盤の演技に修正を加えたことでそうした問題は乗り越えられていたが。
ところで、地点はこれからも《関係》を生産する構造を残したまま、ひたすら諸形式のバラエティーを増やしていくだけなのだろうか? 小さな差異を見出していくこと、自己模倣を退けるためにそこで見えたものに言葉を尽くし自ら退路を断つこと、これは三浦氏が著書で示しているスタンスでもある。かつてアルトーの言葉が孤独の淵にあったように、劇団「地点」が生み出している演劇言語もまた深い孤独の淵にある。そこに耳を傾ける人びとが増えることを祈ってやまない。

▷書評:岡田利規『遡行 変形していくための演劇論』
(シアターアーツ2014年冬号掲載)
演劇論を出版したい。
およそ演劇という表現を手段にいそしんできた者ならば、誰しも一度は考えることだろう。そもそも演劇論とは、「ある一人の人物がもちえた《演劇》についての捉え方を表すもの」だ。しかし同時に、演劇が共同的な関係を前提にしないと成立しない表現形式である以上、稽古場や劇団、そして上演に立ち合った観客をも含めた、その舞台毎に生まれては消えていった《共同体》の記憶を引き継ぐものでもある。自分たちが出逢い、形作ってきた《演劇》の原理を一冊の書物にして残す——文藝賞だとかベストセラーを目指した出版物というよりも、どちらかと言えば物理や数学の研究論文のように、作業仮説と実践の考察による産物であるこの書物は、どこか記念碑的で、現在にとどまらず未来の第三者によって、理解/誤読されていくことを歓迎している。演劇論とは、粛々と実践された苦節の記録であるとともに、同時代の諸問題に正面からぶつかっていくなかで勝ち取られた、いわば認識の叙事詩であった。
こんな経験はないだろうか——演劇史上で所謂《伝説の舞台》と位置づけられている上演の映像を観て、「なんだ、こんなものか(演劇論から想像していたほどじゃないネ)」と、ため息をついたことはないか。ここには《記録の時代における演劇論》という条件が、私たちの眼前に避け難いものとしてあることがわかる。カメラによるクローズアップが自然主義リアリズムの様式に疑問符をつけたように、テクノロジーの発達によって記録する方法やそれを享受することの手軽さが、これまで演劇論と上演のあいだに確固として存在していた隔たりに対して、問いを突きつけ、また新たな関係を創出するだろう。かつてある演劇人が述べたように、「消える脆さをもてる」ことが演劇の目標として潜在しているならば、それらを記録しようとする環境の整備が私たちの知覚様式に何をもらすのか。こうした問いは、演劇論を構成している言葉や記述法に対して、私たちがよく知るそれとは全く違ったものを要請することになるだろう。しかし、記録映像だけでは残せないものがあると信じる/信じられる者によって、これからも演劇論は書かれ続けるはずだ。言葉による伝達の特性が「書かれた言葉の持つ思考を直接的に辿ること」だとするならば、著者によってデザインされた思考経験が持たらす志向性を踏まえながら、そう書かないではいられなかったことについて考えていきたい——どうもそんな読み方すらも、現代の演劇論からは要請されているような気がする。
岡田利規の『遡行』(河出書房新社刊)もまた、こうした条件のなかで書き記された一冊である。この本を大きく特徴づけているのは、岡田の主宰するチェルフィッチュでの活動を主軸に、最近の上演から過去の出世作『三月の5日間』を発表する前後までの、上演の記憶を遡っていく記述を採用していることだ。また、それぞれの制作当時に執筆した文章(エッセイ、ブログ、上演台本、日記、メールによる往復書簡など)を引用し、それらに対して現在の視点で寸評を加えながら、その当時抱えていた《問い》を注意深く取り出し、具体化してみせている点である。ただし、完全に過去に向かって作品ごとに順を追って遡るというわけではなく、問題意識が変遷する時期に区切られており、段階的に遡るように記述されている。
岡田自身、冒頭において、自分の履歴書のようなものを書きたかったわけではないと断り書きがあるものの、本人も認めるように、結果としてそれに近い。興味深いのは、引用されたテクストを「彼ら」と呼び、「むかし撮影されたドキュメンタリー映像みたいなもの」としながらも、現在の視点に優位性をもたせることなく、むしろ寸評と引用テクストを《同格》に扱っている点である。このことは、この演劇論の読み難さにも繋がっている。ある程度は(段階的に遡るとはいえ)時系列通りに展開せざるをえない構成をとっているにも関わらず、環境や条件の変化が作品ごとに強く影響していることを説明していくために、時制の混在を許容するような記述法を選んでいる。ここには取り扱われる出来事それ自体が持つ当事者性を、執拗なまでに操作しない/抽象化しない岡田の姿勢がある。
「現在を取り込まずに過去のことを書くのだとしたら、現在なんてものは存在しないという演技をして書く以外にはない。僕はそういう演技をするのは好きじゃない。」(『遡行』P6)
岡田が敢えてこうした記述法を選んだことを汲んで読むならば、「変形していくための演劇論」という副題が取りたい距離が示すものとは、演劇における諸要素に対しての《手放し方のプロセス》ということだろう。そして、手放されてきたものとは常に《方法論》であり、《形式》のことであった。
それにしても《手放し方のプロセス》とは一体何だろうか。これをただの演出家/演劇作家の変遷として読み取っていいのか。岡田が《方法論》や《形式》と書くとき、思考の光源としているものとは何なのか。岡田は公共という問題に直面した際に、次のように語っている。
「せっかく考えるのであれば、僕は演劇のつくり手なので、できればこの問題を、あくまで演劇の形式的なレベルとか美学的なレベルに落とし込んだところで考えたい。考えた結果をアーティスティックな仕方で自分にフィードバックして、そのおかげで新しい形式に到達できた、みたいなことになったらいちばんいい。」(『遡行』P123)
《形式》とは、岡田にとって「新しい」ということの導きであるとともに、演劇作家としての思考の誠実さを測る「《場》のようなもの」と言えるのかもしれない。この作法は、『遡行』の通奏低音として一貫している。同時に、ここにおいて示されている態度とは、《形式》に先立って個人の思想や政治的な問題といったものを提示するまいというものでもある。
たとえば震災を経た後に「日本の社会にとって芸術が、中でもここでは演劇が、必要であると言える根拠は何か?」「(演劇に従事する人たちによる)演劇の必要性なり公共性を唱えるロジックが、自分たちの存在意義を正当化する屁理屈ではないとどうしていえるのか?」と岡田が書くとき、そこにはもっともらしく演劇が社会に有用とされていた言説に対する苛立ちが見えるし、その一方で本当に演劇に向けて語られるべき言葉とは何かということを確かめる手続きのようにも思える。
こうした態度は、かつてイデオロギーが演劇の推進力であった時代の感性からも随分と隔たっているし、先行世代が持っていた歴史性や集団論からも岡田自身が自由であることからもわかる。
「演出家の理論は、いずれも、決して純粋な科学的な視点から出てきたものではない。そのときの演劇状況、あるいは劇団や、俳優の環境に大きく左右されて、その論が立てられている。そのことを抜きにして、教条的に、ある演劇論を信望しても、それはまったく意味をなさない。その思想が出てきた背景を考えて、ある歴史的位置づけを行なうという思想史的な作業は、演出という仕事を考える上で欠かせないものなのだ。」(平田オリザ『地図を創る旅 青年団と私の履歴書』P104)
ここで岡田の先行世代にあたる平田オリザが意識しているのは、《形式》や《方法論》といったものを左右する《条件》についてである。かつて平田は、『演劇入門』(講談社現代新書刊)において、美学の先鋭化や体系化、名優たちの藝談などによってその実体を神秘的に覆ってしまう先人たちの演劇の言説に対し、ハウ・ツー本形式の、具体性をもった技術論としての演劇論を書くことによって、 従来の日本の演劇論が陥りがちであった傾向そのものに批評的態度を示した。しかし、ハウ・ツーという手軽さを選択できた平田においても、岡田からみるとまだ「重い」し、演劇について向けられる言葉が多いと感じるのではないだろうか。正しいか間違っているかよりも、「おもしろいかつまらないか」を基準に《形式》が取り出されている点でも大きな意識の差がある。
『遡行』では、チェルフィッチュの活動を主軸に書かれているにも関わらず、集団論や俳優教育といった側面にはほぼ触れられていない。岡田の取りまとめている創作体制が大きく作用しているに違いないにしろ、従来の演劇論というものに触れてきた者からするとちょっとした空白を感じるのではないだろうか。だが仮に、ここにも岡田が《形式》を求める際に気を払っている「こわばり」や「硬直性」といったものが見出されていたとしたら——つまりこういうことだ、周到に記述を避けているこれらの諸問題に対して、従来の演劇論が持っていた最も窮屈な側面を「些細な問題」へと読替えたのではないだろうか。言い換えると、『遡行』にある切断的な読書構成を取ることで、自身の成長譚と並行して触れざるをえないはずの集団論や俳優教育についての考察を回避しているのではないか。もっとも、ただひたすら自分のことしか責任をもって語れないという素朴な態度のあらわれでしかないかもしれないのだが。
岡田にとって最重要事項は《形式》であり、《方法論》であった。もちろん従来の演劇論のように、ある形式や美学の研鑽にあわせて、それを支えるための抽象的な記述を受け入れることができた時期があったことを、岡田は認めている。もともと岡田自身は、《方法論》を緻密に組み上げたいという欲求を強く持つ演劇作家だった(例えばチェルフィッチュのHP上にある、スピノザの『エティカ』式に書かれて頓挫したままの演劇論は、その傾向を物語っている)。だが協働する役者たちと、《方法論》が持たらす磁場について考察を重ねていくにつれて、そこへの執着や行き詰まりを「袋小路」と呼び、俳優への影響力の強さに対しては「暴力」という言葉をあてるような感性が、岡田の中で培われていく。演劇論を記述する際に働いた《同格》を志向する感覚のことを考えると、これは当然の帰結なのだろう。
《方法論》がもたらす統一感や画一性への警戒、「ある価値観は限られた射程をしか有しない」として、自身のスタイルとして周知されていた《形式》をアクロバティックに手放していく。また役者にとって、「補助輪としての《方法論》」から「最低限の条件としての《方法論》」へと移行と、稽古場における関係性そのものをも変化させていった。《方法論》が、役者の自由を支えるために機能するようになったとき、岡田は「なぜそれが良いことがと思うかと言えば、人のことを信用できるのは良いことだからだ」と言ってのけている。そこには美学の探究よりも、役者との関係の解放に対する信頼が宿っている。その傍ら、工学的な知覚構成とも言えるものを積極的に演出に持ちこんでいった。だが、ここでも演出上の倫理を問うかのような逡巡をすることになる。
「(観客の)脳内に電気を流して特定の反応を与えるというようなことに近いことが、頭に電極をさし込んだりすることなしにパフォーマンスによって観客に対して行うことはできるんだな、とこのとき僕は完全に確信したのだ。そしてそう確信したと同時に、でもそれってちょっと怖いことだなというふうにも思った。パフォーマンスがそんなふうにただの機能の塊と化したら、それはそれで袋小路に行着いてしまう。」(『遡行』P239)
時折岡田が口にする素朴な問いについて、文字通りに受け取ろうとすると大概の人々は面食らってしまうに違いない。彼は最新作を説明する際に、「ドラマとキャラクターのはたらきがわかった」と屈託なく書く。また「演劇は、やる側と見る側とが、これは演劇である、という約束事に合意した上で成立している」という、ごく当たり前のような事実に素直に驚いてみせる。こうした《演劇以前》への問いが彼の演劇論の端々を支えている。
「芸術の機能とは何かという定義を書き換えることだ。そんな壮大なことが自分にできるとは到底思わない。けれど、それはともかく、そういうことをしたい——」おそらく、岡田はこの目標を明確な定義として言葉に表すことはしないだろう。だが、逡巡を辞さずに演劇の持つ可能性に素直に驚き続けることが、いつか誰かによって読まれる軌跡になることは知っている。《記録の時代における演劇論》は、素朴に問う勇気とともにある。

Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.